2025/04/03
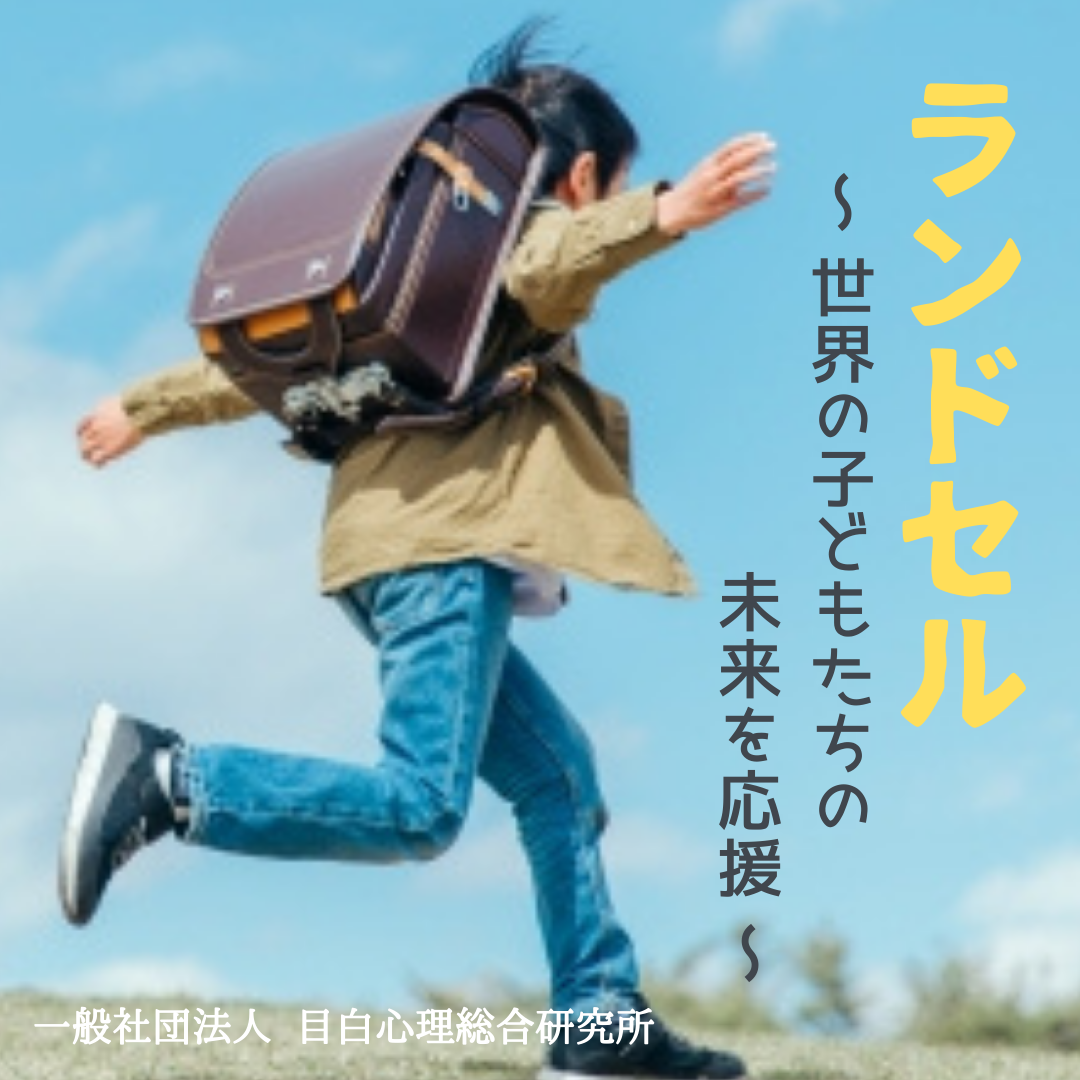
いよいよ3月も終わり4月になると、新年度・新学期に入ります。
入学式を迎えるご家庭では、これから始まる新しい学校生活に備えながら、期待に胸を膨らませていることでしょう。
でもなぜか「ランドセル」は、1年前から準備をする風潮が広まっていて、今では「ラン活」という言葉も定着してきていますね。
今回は、日本独自の文化ともいえる、箱型で背負式の「ランドセル」についてお話をしたいと思います。
ランドセルの発祥は、明治10年に開校した学習院初等科とされ、子どもたちは、馬車や人力車で通ったり、使用人に荷物を持たせるなどして通学していました。
しかし、「学用品は自分の手で持ってくるべきだ」とされ、明治18年に採用されたのが、江戸時代にオランダからもたらされた軍隊用の背のう「ランセル(ransel)」で、それがいつしか「ランドセル」と呼ばれるようになったといわれています。
「リュック形の背のう」が、現在のような「箱型ランドセル」に変わったのは明治20年。
のちの大正天皇が学習院初等科にご入学される際に、お祝いとして伊藤博文が献上した「箱型ランドセル」が原型となり、その後、黒色で形状や寸法などが統一された「学習院型ランドセル」が完成し、100年以上経過しても基本的なスタイルはまったく変わっていません。
「ランドセル」は、軍用カバンがルーツゆえ、強度のある牛革を使用した高級品なので、当初は都市部の上流階級の家庭のみ、つまり、地方や一般家庭の子どもたちは、布製のカバンや風呂敷を使用していました。
その後、「ランドセル」が庶民に広まったのは、戦後の昭和30年代からでした。
色は男の子は黒、女の子は赤が主流で、昭和40年前後になると、人工皮革が価格や特徴の面で素材として採用され、シェアを広げていきました。
平成に入ると、ピンクや緑、水色などのカラーバリエーションが豊富になり、今ではジェンダーレス化して、性別に関係なく自分が好きなカラーやデザインを選べるようになりました。
しかし、逆にこの3月で小学校生活が終わり、「ランドセル」が不要になってしまったご家庭もあるのではないでしょうか。
実は、「ランドセル」は、寄付をすることができるのです。
「ランドセル」を必要としている子どもたちが、世界中にたくさんいます。
発展途上国など、経済的に困難な状況にある子どもたちに「ランドセル」を届けることで、教育を受けるきっかけとなり、さらに、学習意欲を高めることができるなど、子どもたちの未来の支援に繋がります。
特に「女の子に勉強は必要ない」という考え方が根強い地域に、男女平等に「ランドセル」を配ることで、「女の子にも学ぶ権利がある」と周囲に認識づけることができます。
また、自分の子どもにも、リサイクルの大切さや社会貢献の大切さを教える機会にもなります。
ただし、送る先の国によっては、宗教上、本革を使った「ランドセル」や、あまりにもボロボロな「ランドセル」は送ることができないことと、基本的には、支援団体までランドセルを送る際の郵送費は寄付する側の負担になりますので、事前に確認が必要です。
お問い合わせは、ホームページ「お問い合わせ」からお気軽にお声がけください。
「ランドセル」の寄付は、単に物を送るだけでなく、子どもたちの未来を応援し、持続可能な社会づくりに貢献するという、大変意義深い行為といえますね。
[ 一般社団法人 目白心理総合研究所 ]
臨床心理士 / 公認心理師 / キャリアコンサルタント
/ CEAP / EAPコンサルタント /
CBT Therapist®︎ / CBT Professional(EAP) / CBT Extra Professional ®︎
目白駅から徒歩2分
池袋駅から徒歩10分

